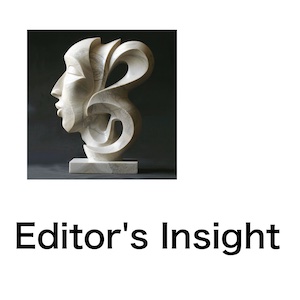ロボタクシーの運行数が世界的に拡大しています。
Alphabet の自動運転部門 Waymo は毎週 20 万回、月間約 80 万回のライドを提供しています。GM の Cruise 部門撤退により、現在米国で無人運転タクシーを提供する主要企業はほぼ Waymo のみとなっていますが、テスラは急速に同社の自動運転ソフトウェア、FSD( Full Self Driving )を進化させつつあり、2026 年にはロボタクシーサービスに本格的に参入すると公言しています。
一方、中国市場では複数の企業が急速に市場を拡大しています。Baidu Apollo が直近四半期で週 84,000 回(四半期で 110 万回)のライドを提供し、Pony.AI も週 26,000 回のライドを実現しています。AutoX は 1,000 台の車両を稼働させ、WeRide も積極的にサービスを展開していますが、両社はライド回数を公表していません。これら全てを合計すると、全世界の無人ロボタクシーによるライドは月間で 130 万回以上に達している計算になります。
多くの人はロボタクシーを Uber の代替や公共交通の補完と捉えていますが、それは表面的な理解に過ぎません。各企業が数十億ドルという巨額の資金を投資している本当の目的は、単にタクシーやトラック運転手を置き換えることではありません。現在のサービス提供は「実験段階」であり、ユーザーの利用パターンや需要を把握するためのプロセスだと考えられています。データ収集と技術改良を通じて、より大きな変革への基盤を構築している段階といえるでしょう。
ロボタクシー企業が真に狙うのは、Uber や Lyft が年間約 600 億ドルを稼ぐライドシェア市場ではなく、約 5 兆ドル規模の「地上輸送産業全体」の変革です。長期的には「車の所有を不要にする未来」を目指していると言われています。これは単なる移動手段の提供にとどまらず、都市設計、生活様式、土地利用など社会全体に影響を与える壮大な構想です。
もちろん、この変革は一気に起こるわけではなく、段階的に進むと考えられています。テスラが構想する計画では、所有者が使用していない間、自分が所有するテスラが自動的にタクシーサービスを提供して収益を生み出すとされています。テスラオーナーにとっては、車が単なる移動手段ではなく、収益を生み出す資産になるという発想の転換です。短期〜中期的には、この「車を所有しながら投資資産としても活用する」モデルが普及するでしょう。
このモデルが浸透すれば、高度なセンサー類やソフトウェアを備えた高額な自動運転車への投資が、不動産投資のように収益性に基づいて評価されるようになるかと思います。すなわち、「この車は年率何 %で投資が回収できるか」という観点から購入判断がなされるようになるでしょう。そうすると、ロボタクシー対応の車がたとえ高額な車両になったとしても、安定した収益が見込めるならば合理的な投資と判断されることになるでしょう。
また、融資を行う金融機関も収益予測に基づいた融資判断が可能となれば、従来よりも高額な車両への投資が正当化されます。「この車は月にいくら稼げるか」という収益性が与信審査の重要な要素となり、与信の基準が変わるとともに、新たな金融商品も登場してくるはずです。
また、車が 24 時間稼働するようになると、都市の風景も変わっていくでしょう。一時的な待機所としての駐車場ニーズは残りますが、それは都心にある必要はなく、駐車した後の利便性を考えた従来型の駐車場需要は減り、その土地は別の用途に転換されると思います。また、一台あたりの走行距離が大幅に増えることにより、燃料消費や部品の摩耗が進み、ランニングコストが増加することが考えられます。そうすると、メンテナンスの頻度や方法も現在の自家用車とは大きく異なってくるでしょう。
車が投資資産となれば、中期的には、効率的な資産運用を求めて、個人オーナーよりも大規模な資本による参入も進むと思います。そうして大手企業や投資ファンドにバックアップされた大資本が大量の自動運転車を保有・運用するようになると、次第に小資本の個人オーナーは市場競争力を失い、市場から徐々に排除されていく可能性があります。最終的には、現在の大構想のように、多くの人が車の「所有」から「利用」へとシフトし、必要なときに車を呼び出して利用するというスタイルが一般的になっていくのではないでしょうか。
こうした変化は自家用車だけでなく商用貨物車にも同様に起こると予想されます。物流業界でも無人運転技術の導入が進み、輸送コストの削減と効率化が図られるでしょう。24 時間稼働可能な無人トラックが普及すれば、物流のあり方も根本から変わる可能性があります。
ただし、この変革が本格的に進むためには大幅な規制緩和が不可欠です。現在は特定の国(アメリカと中国)において、都市を限定した規制緩和、が中心で、高速道路などを利用した都市間移動への適用にはさらに時間がかかるとみられています。各国・各地域の交通法規や保険制度の整備、事故発生時の責任所在の明確化など、解決すべき法的・社会的課題も少なくありません。また、サイバーセキュリティへの対応など、技術的な課題も多く残されています。
このように、ロボタクシーの発展は、単にタクシードライバーの仕事がどうなる、という問題にとどまらず、今後の「モビリティ」に対する考え方そのものを根本から変える可能性を秘めています。長期的には車は所有するものから利用するサービスへと変わり、都市設計や生活様式にも大きな影響を与えるでしょう。
現在は過渡期の始まりに過ぎませんが、今後 数十年の間に私たちの移動の概念は大きく変わっていくことになりそうです。今までは絵空事に過ぎなかったものが、ロボタクシーの実証実験が進み、技術的・社会的な課題が一つずつ解決されていく中で、新しいモビリティの時代へ一歩ずつ確実に歩みを進めています。
参考:”Robotaxis, Mostly Waymo, Are Giving 1.3 Million Rides/Month. Why?” Forbes, Mar 07, 2025