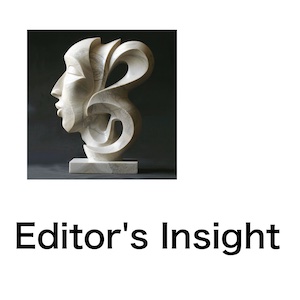AI で急増する水需要
AI 技術の急速な普及により、データセンターの水使用量が 2028 年までに最大 4 倍に増加する可能性が指摘されています。現在、米国のデータセンターは年間 170 億ガロン(約 640 億リットル)の冷却用水を直接消費していますが、これが 2028 年には 1,280~2,560 億リットルまで拡大すると予測されています。
この増加の背景には、AI 専用サーバーの圧倒的な発熱量があります。従来のサーバーと比較して AI 処理に特化したチップは大幅に多くの熱を発生させ、その冷却には膨大な水が必要となります。多くのデータセンターで採用される「蒸発冷却方式」では、取り入れた水の約 80% が蒸発で失われてしまっています。
水不足地域での建設ラッシュという矛盾
より深刻な問題は、新しいデータセンターの立地選択にあります。Bloomberg の分析によると、2022 年以降に建設または開発中のデータセンターの約 3 分の 2 が、既に「水ストレスの高い地域」に位置しています。テキサス州やアリゾナ州など、干ばつが深刻化している地域に AI データセンターが集中して建設されているのです。
この一見非合理的な立地選択には、明確な経済的理由があります。これらの地域は(地域で採掘されている化石燃料や太陽光などの自然エネルギーにより)電力コストが比較的安く、広大な土地確保が容易で、州の方針により税制優遇措置も充実しています。こうした理由により、データセンターの建設が急ピッチで進められています。
こうした地域では実際の影響も既に現れています。ジョージア州では Meta のデータセンター建設により近隣住民の井戸水が枯渇し、住民が飲料水の確保に苦労する事態が発生しました。また、バージニア州ラウドン郡では、AWS のデータセンター群により地下水位が年々低下し、地域の農家が灌漑用水の確保に苦労している状況です。
企業の環境対策と現実のギャップ
大手テック企業は環境対策として様々な取り組みを発表していますが、その実効性には疑問が残ります。Google、Microsoft、Meta は 2030 年までに「 Water Positive(使用する水よりも多くの水を環境に戻す)」を達成すると宣言していますが、現在の各社のデータセンター拡大計画を考慮すると、この目標達成は極めて困難と予想されます。
さらに問題なのは、多くの企業がデータセンターごとの水使用量を「企業秘密」として公開を拒んでいることです。この透明性の欠如により、地域住民や行政は適切な判断を下すことが困難になっています。一部の企業は再生水の利用や、水の蒸発を防ぐ「閉ループ冷却システム」の導入を進めていますが、これらの技術は初期投資が高く、業界全体での普及は遅れているのが現状です。
複合的な環境負荷の拡大
水使用量の問題は、エネルギー消費の急増と密接に関連しています。2028 年までに米国のデータセンターは全国電力の 12% を消費する可能性があり、この電力を生産するためにも大量の水が必要とされます。火力発電や原子力発電では、施設の冷却のために 1 キロワット時の電力生産に 1~2.5 リットルの水を消費するため、間接的な水使用量も爆発的に増加することになります。
国際的な波及と格差の拡大
この問題は米国内に留まりません。ウルグアイでは Google が計画していたデータセンターが地域の水不足懸念から住民の強い反対を受け、建設が延期されました。チリでも Amazon のデータセンター建設により農業用水の確保が困難になるとして、地元農民が抗議活動を行っています。また、オランダでは住民の反対により Microsoft のデータセンター計画が中止されるなど、地域住民の声が政策に反映される例も見られます。
政策対応の立ち遅れ
現在、データセンターの水使用に関する包括的な規制はほとんど存在しません。カリフォルニア州が大規模データセンターに対する水使用量報告の義務化を検討しているものの、まだ成立していません。また、連邦レベルでも AI の環境影響を測定する法案が提案されていますが、業界の反対により進展が遅れています。
一方、EU では 2024 年から大規模データセンターに対してエネルギーと水の使用効率の報告を義務付けるなど、規制強化の動きも見られます。しかし、グローバルな AI 競争の中で、環境規制が厳しい地域から規制の緩い地域へとデータセンター建設が移転していく傾向も見られ、ある特定の地域で規制を強化しても問題の根本的な解決にならないと懸念する声もあります。
持続可能な解決策に向けて
この問題を解決するには、技術革新、政策改革、企業責任の三つの要素を同時に進める必要があります。
1)技術面では、水の消費を抑えたより効率的な冷却技術の開発と普及が急務です。液体冷却システムや海底データセンターなど革新的なアプローチも検討されていますが、コストや環境影響の課題があり、大規模な普及や実用化には時間がかかります。
2)政策面では、データセンターの水使用量に関する透明性の確保と環境影響評価の義務化が不可欠です。また、アメリカ国内ではアラスカ、ヨーロッパではノルウェーやアイスランドなど、安価な電力確保の可能性があり、水が豊富で気候の涼しい地域への立地誘導策も検討すべきでしょう。
3)企業責任としては、水使用データの公開と地域社会との対話の深化が求められます。短期的な利益追求を超えて、長期的な環境保護と地域社会の福祉を重視した経営方針への転換が必要です。ただし、こうした転換を促すためには、企業が持続可能な取り組みを行うことで競争上の優位性を得られるようなインセンティブ構造を政策的に整備することも重要となります。
まとめ:問題の本質を見極める
ここまでデータセンターの建設で急増する水需要について書いてきました。ただ、データセンターの水使用について冷静に分析すると、全米規模のマクロで見た場合の影響は実は限定的です。データセンターの水利用は現在のところ全米総取水量の約 0.01% にすぎません。また、火力発電の冷却水再利用などの技術革新によって、むしろ米国全体の総取水量は 1970 年代のレベルまで減少しているのです。
そうしたマクロ的な視点で考えると、「データセンターの水使用急増が全米の水資源に大打撃を与え、将来的に水不足に陥る」といったように過度に危機感を煽る論調には疑問を感じます。
ただし、確かに、全体を見るマクロ的な視点だけでは、問題の本質を見誤ることになります。真の問題は、上述の通り、データセンターが建設される地域にあります。新設されるデータセンターの多くが、もともと「(テキサスやアリゾナなど)水ストレスの高い地域」に集中していることです。こうした地域に大量の水を消費する施設が建設されると、局所的な水不足を加速させることになります。また、これらの地域は、大量の水を消費するシェール油田・天然ガス生産地域とも重なることが多く、地域レベルでの水資源への圧迫が深刻化しています。
ただし、データセンターの水消費問題は、技術的な解決策により中期的には改善が可能と思われます。現在はコストの安さから「蒸発冷却方式」が採用されていますが、この方式では水の 80% が失われてしまいます。これを「閉ループ冷却システム」や「液体冷却」に転換していくことにより、水消費量は大幅に削減可能です。もちろん初期コストの問題はありますが、他の水利用分野と比較すれば、データセンターの水利用は対処可能なレベルまで引き下げることができると考えています。そのため、2028年に全米の12%にまで急増すると見られるデータセンターの電力消費の問題と比べるとそこまで深刻な問題だとは筆者は考えていません。
ここから少し話がそれますが、アメリカにおいてより深刻な水資源問題は、実は農業分野にあります。米国の総取水量の約 35% は農業で使用され、農業用水は再利用ができないため、「消費される水」という観点では米国の水消費の 80~90% を農業が占めています。
さらに話がそれますが、特に懸念されるのは、米国の穀倉地帯であるグレートプレーンズの地下に広がるオガララ帯水層です。この帯水層は米国の作物生産の 5 分の 1 を支え、国内灌漑用水の 30% を供給する重要な水源ですが、数百万年前に形成された「化石水」であり、特に南部においては現代の降雨による補給はほとんどありません。この地域の経済的繁栄は、有限な資源の採掘という持続不可能な基盤の上に成り立っているのです。(そしてこの南部には上述のデータセンターとシェール採掘エリアが重なってきます・・・)
データセンターの水使用問題も重要ですが、世界の(数少ない)穀倉地帯の一つであるグレートプレーンズで進行している持続不可能な水利用こそ、より本質的で長期的な危機として対処すべき課題と考えています。