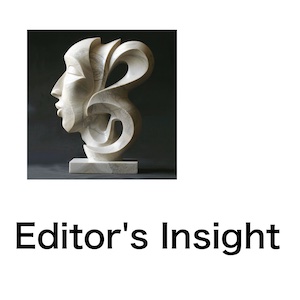2025年第2四半期決算を受け、クラウド業界の競争構図が激しい動きを見せています。業界2番手のMicrosoft Azureは AI 推論需要で急成長を続ける一方、最大手の AWS は主にGPUの供給制約により成長が鈍化。3社の中で一番規模の小さい Google Cloud は堅実な戦略実行により成長と収益性の両立を着実に実現しています。
AI ブームが Azure の市場シェアを押し上げ
Microsoft Azureを含む Intelligent Cloud部門の売上高は 299億ドル(約4兆4100億円)を記録し、前年比 26%の成長となりました。Azure 単独( IaaS/PaaS 推定)では 222億ドル(約 3兆 2700億円)で成長率 39%と圧倒的な勢いを示しています。特に AI サービスが約 30億ドル(約 4420億円)の売上を上げ、成長の 19%に寄与しました。
Satya Nadella CEO は「クラウドと AI が全産業の変革を駆動している」と強調し、OpenAIとの連携によるGPT モデルの活用が強みとなっています。AI 推論ボリュームは前年比 90% 増と飛躍的に拡大し、GPT-5 リリースでさらに 40% の成長が見込まれています。
しかし、Azure も供給制約の影響を受けており、同社は 2026 年前半まで制約が続くと予測しています。対策として、ソフトウェア効率向上により GPU 当たりのトークン処理能力を大幅に改善し、限られたハードウェアリソースでの最大化を図っています。ただし、AI 推論比率の増加により、クラウド粗利益率は 2 ポイント低下するという課題も抱えています。
AWSは供給制約で成長鈍化
クラウド市場の首位を走る AWS は、売上高 309 億ドル(約 4兆5600億円)で前年比 17.5%の成長にとどまりました。年間売上(ARR)は 1240億ドル(約 18兆3000億円)規模に達して依然として首位を維持しているものの、成長率では競合に遅れをとっています。
最大の要因は深刻な供給制約です。Andy Jassy CEO は「需要が供給を常に上回っている状況」と説明し、特に GPU 不足とデータセンターの電力容量不足が成長を阻害しています。この問題は業界全体に共通する課題で、AI 需要の爆発的増加に対してインフラ整備が追いついていない状況です。
AWS は供給制約の解消に向けて「数四半期(2026年中)」での改善を見込んでいます。具体的な戦略として、自社開発の Trainium チップによる NVIDIA GPU 依存度の軽減や、Bedrock サービスでの効率的なAI 推論基盤の構築を進めています。しかし、バックログは 1950億ドル(約 28兆7000億円)と堅調な一方で、営業利益率は 32.9%に低下し、競合が進める AI 統合と比較して遅れているとの指摘もあり、市場シェアがさらに侵食される懸念が高まっています。
Google Cloudが成長と収益性を両立
3社の中で最も規模が小さい Google Cloud ですが、売上高 136 億ドル(約 2兆100億円)で前年比 32% の高成長を達成しました。売り上げ的には AWS の 309 億ドルの約半分以下、Azure を含む MicrosoftのIntelligent Cloud 部門 299 億ドルと比べても大きく差があります。しかし、規模の小ささを逆手に取った機動力のある戦略が功を奏しています。
GCP( Google Cloud の IaaS/PaaS 部門)では 72億ドル(約1兆600億円)で成長率約 39% と Azure に匹敵する勢いを見せています。市場シェアは約 13% と AWS の約 30%、Azure の約 21% に大きく劣りますが、高い成長率を維持しています。
Google Cloud も他の2社と同様、容量不足の影響を受けており、同社は 2026 年まで制約が続くと見込んでいます。しかし、自社開発の TPU(Tensor Processing Unit)や Gemini モデルの最適化により、効率的な AI 処理を実現する戦略を取っています。また、収益認識を調整しながら顧客需要に対応する柔軟性も見せています。
また、供給制約に対して、即座に全サービスを提供できない場合でも、大型契約を締結し、段階的な提供スケジュールを顧客と合意することで、競合他社に顧客を奪われることを防いでいます。この方法により、契約の収益計上タイミングを供給能力に応じて調整し、将来の安定した収益源を確保しながら顧客関係を維持する戦略的な対応を見せています。
注目すべきは、供給制約がある中でも営業利益率を 20.7% まで大幅改善している点です。これは、前年比 9 ポイントの改善となっていて、複数の要因が重なった結果です。第一に、AI 関連需要の拡大により売上高が32% 成長し、規模の経済効果が働き、データセンターや人件費などの固定費比率が低下しました。第二に、Geminiモデルを中心としたAIソリューションの展開により、従来のクラウドサービスより高収益な分野へのシフトが進んでいます。第三に、大型契約の増加により営業効率が向上し、安定した収益基盤を構築できています。今まで規模が小さかっただけに、この辺りが他の2社と比べて収益性の改善につながりやすいということが背景にはあるかと思います。
こうした改善により、Google Cloudは成長と収益性の両立という難しい課題をクリアしているようにみえます。Sundar Pichai CEOは「顧客需要が強く、2500万ドル超(約 37億円)の大型契約件数が倍増している」と述べており、実際にバックログは 1,060 億ドル(約 15兆 6000億円)に達しています。規模では劣るものの、競合が課題を抱える中、Google Cloud は確実に成果を積み上げる堅実なアプローチで存在感を高めています。
巨額投資競争と供給制約解消への道筋
供給制約の根本原因は、生成 AI 需要の爆発的増加に対してインフラ整備が追いついていないことにあります。特に GPU などの半導体不足と、データセンターの電力容量不足が深刻化しています。各社はこの問題を解決するため、収益規模で圧倒的に勝る AWS が年間 1,120 億ドル(約 16兆 5000億円)、Microsoftが 800億ドル(約 11兆8000億円)、最も規模の小さい Google Cloud でも 850億ドル(約 12兆5000億円)の設備投資を予定しており、三社合計で約 2,400億ドル(約 35兆3000億円)という史上最大規模の投資競争が展開されています。
各社の解消戦略とタイムフレームは異なりますが、おおよそ 2026年までは供給制約が続くと見込まれています。
ただ、現状では AI サービス売上は投資の 10% 程度の回収にとどまっており、数年単位での回収期間を見込む必要があります。特に Google Cloud は収益規模に対して相対的に大きな投資を行っており、将来への積極的な布石を打っています。アナリストは「今後、各社の供給制約解消のタイミングのずれが、各社の競争力を左右する重要な分岐点になる」と指摘しています。